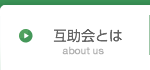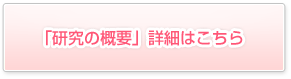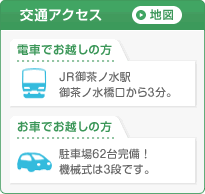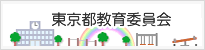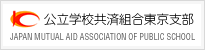新しい教育を考える会
豊島区立清和小学校
研究テーマ
- 信頼される教師になる~教師の資質向上を目指して~
研究期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
研究結果の概要
研究経過
本年度の基本方針
「新しい教育を考える会」は、30年程前に主体的に学び続ける教師を育てることを趣旨として宮本朝子先生が初代会長として発足された会です。その後、藤原孝子先生、斎藤純先生が会長として歴任され、令和2年度より私が会の運営を引き継いでいます。新型コロナウイルスの発生から3年余りが経ちました。この間「教師の学びを止めない」を基軸に、オンライン開催をしてきました。令和4年度は、11回のオンライン研究会を通し、教科・領域・教育課題の研究を深めることができました。皆さんのご理解・ご協力により、この3年間、無事に研究会を開催できたことに心より感謝申し上げます。
さて、令和3年度の国立、公立、私立の小・中・高・特別支援学校におけるいじめの認知件数は、約61万5千件、小・中・高等学校における暴力行為の発生件数が約7万6千件、小・中学校の不登校児童生徒件数が約24万5千人等の結果が明らかになりました。新型コロナウイルス感染症の影響が続き、学校や家庭における生活や環境が大きく変化し、子供たちの行動等にも大きな影響を与えていることがうかがえます。学校は、組織としての対応力、一人一人の教師によるより深い児童・生徒理解力が求められています。そこで、これまでの教科・領域に加え、「特別活動」「学級経営・児童理解」を設定しました。今年度も授業の実践や子どもの学びの姿から共に考え、何より私たち自身が主体的に教育活動に関わっていくことが、教育者としてのやりがいにつながっていくと考えます。
また、東京都より「東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質向上に関する指標」について「教師に求められる資質能力」を5つの柱で整理して示されました。
①教職に必要な素養
②学習指導
③生徒指導
④特別な配慮や支援を必要とする子供への対応
⑤ICTや情報・教育データの利活用
これらの教師に求められる資質能力を踏まえ、本研究主題を「信頼される教師になる~教師の資質向上を目指して~」としました。
政府は、新型コロナウイルスの感染法上の分類を5月8日から、季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げると決めました。本研究会では、6月より参集・対面という形に戻し、研究会を開催してまいります。
今後も、これまでの研究会の伝統を継承し、激動する時代の中で育むべき資質・能力に対応した内容を共に考える研究会を運営していきます。
その他 特記事項
4月・5月は、月1回、研究会をオンラインで開催しました。
6月からは、参集(豊島区教育センター)、オンラインのハイブリッドで開催しました。
新潟、岡山の教員や産休の教員もオンラインで参加しました。