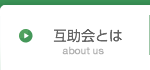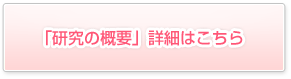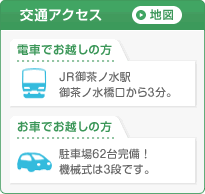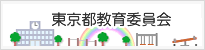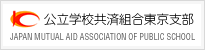府中市立府中第三小学校
府中市立府中第三小学校
研究テーマ
- 進んで問題解決に取り組む児童の育成
〜既習や友達とのつながりに価値を見いだす算数科の学習を通して〜
研究期間:令和5年4月19日から令和6年2月29日まで
研究結果の概要
研究テーマ設定の理由
算数科の学習における数学的活動は、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付けたり、思考力、判断力、表現力等を高めたり、算数を学ぶことの楽しさや意義を実感したりするために、重要な役割を果たす。そのため、学習者である児童が「数学的活動を楽しめること」「自ら問題を見いだし、解決すること」「友達と考えを伝え合うことで学び合ったり、学習の過程と成果を振り返り、よりよく問題解決できたことを実感したりすること」を意識して授業づくりを進めることが求められる。そして、既習事項を基に自分の考えを筋道立てて伝えたり、互いの考えについて「共通性」や「他の場合」に着目しながら聞いたりするといった「考えのつながり」に価値を見いだし、進んで問題解決に取り組む児童を育んでいきたいと考えた。
以上のことを踏まえ、今年度の研究主題を「進んで問題解決に取り組む児童の育成 〜既習や友達とのつながりに価値を見いだす算数科の学習を通して〜」と設定した。
研究の進め方
- 研究主題に迫るための手だてとして、
- 本時で目指す児童の姿の明確化
- 既習事項とのつながりを見いだす工夫
- 友達の考えとのつながりを見いだす工夫
- 授業後は、毎回少人数のグループに分かれて協議を行った。Googleジャムボードを使い、成果や改善案、質問等を共有しながら協議を進めた。
- 3〜6学年の児童を対象に、算数の学習に対する質問紙調査を年2回(5月と12月)行い、調査結果を分析する。なお、質問紙調査はGoogle フォームを活用した。
研究の成果
- 教師は既習や児童同士の考えをつなぐことを意識した発問を心掛けるようになり、日々の授業づくりにも活用していくことができた。
- 全学年による研究授業を参観したことで、各学年の算数の内容や系統性を把握することができ、何を既習として習得しているのかを確認するようになった。
- 児童は「前に習ったことを使えば、新たに問題解決できる」との意識が芽生え、既習事項を確認するために、ノートを見返す学びの姿が見られるようになった。
- 児童は、相手意識をもって話すことできるようになり、他者との考えのやり取りの価値に気付く発言も見られるようになった。
- 考えの全体共有の場面において、他の児童の考えが書かれた板書を基に、別の児童が説明する場面を設けるようになったことで、筋道を立てて説明する力が養われた。