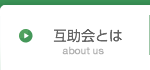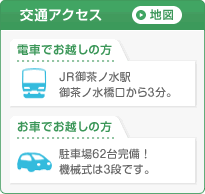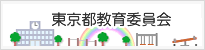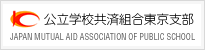教育研究グループ支援(研究成果報告)
くほんぶつ教育研究会
代表者 東みどり
学校名 世田谷区立九品仏小学校
研究テーマ
- 「小学校1年生の学校生活への適応」 ~地域・家庭との連携を通して~
研究期間:平成24年5月1日 から 平成25年3月31日まで
研究結果の概要
【1】研究主題設定の理由
本校は住宅街にあり落ち着いた地域にある。学校選択制を採用していない世田谷区にあって、本校の学区内に居住している就学児童のうち約4割が私立小学校や隣接する公立小学校へと指定校を変更する。そのため本校は、2学級編制可能な就学児童が居住しているにもかかわらず、1学年1学級編制となる。
一度、単学級の学校となってしまうとなかなか抜け出すことが難しい。それは、一部の保護者に小規模校を避ける心理が働くからである。まず、いじめなどがあったときにクラス替ができないこと、6年間同じクラスで人間関係が固定化すること、PTA活動の負担が大きいことが危惧されている。これらは客観的なデータがないのにもかかわらず保護者どうしの口コミで広がっている。
卒業生や地域から愛されている。本校が地域の公立学校として存続していくための児童数確保が最大の学校経営の課題であることは言うまでもない。学区に居住する就学児童の流失を抑えるために、就学児童とその保護者に対するはたらきかけ、および、就学後の児童に対する指導の充実が大切と考え、下記の方策の有効性について研究に取り組んだ。
【2】小学校1年生の学校生活への適応の取り組み
(1)児童による保育園児との交流
1. 4年生による保育園での読み聞かせ活動

写真1 保育園での読み聞かせ
6月、読書活動を通しての小学校と保育園の子どもたち同士の交流が実現し、4年生の児童が学校の近くの奥沢西保育園で読み聞かせを行った。保育園のテラスやホールなど思い思いの場所で、お母さんが我が子にするように膝をつきあわせて絵本を読んであげる姿が微笑ましかった。
保育園児にとって、小学生と触れ合うことで、小学校生活への憧れを高めることがきる。保育園児の保護者に本校児童の姿を見てもらうために保護者会があるときに日程を組むようにした。自分の子どもがどのように成長していくかのイメージをもつことは、子育ての参考になると考えた。また、本校児童にとって、園児に喜んでもらえたことで、自尊感情が高まりが見えた。
2. 1年生による園児を迎えての学校探検

写真2 学校の雛人形を見る園児

写真3 下駄箱の使い方を聞く園児
2月下旬、小学校入学まで1ヵ月となった園児を学校に招いて、1年生児童が学校を案内する活動を生活科の時間に設定した。
保育園・幼稚園に慣れ親しんだ園児にとって、学校はあまりにも大きく、不安である。小学校入学後に登校渋りとなる1年生もめずらしくない。その不安を和らげるため、事前の学校体験は有益であると考えた。案内も教師である大人が行うよりも、年長児のすぐ年上の1年生がすることで、より学校が身近に感じるはずである。
学校探検当日、20名の年長児が来校した。玄関で待ち受けた1年生は、一人ずつ園児の手を取り勇んで自分たちの教室や図書室等を案内した。学校の様子を知ることによって園児に安心感をもたらし、小学校生活に適応していく下支えになると共に学校生活への希望をより一層強くもたせることができた。
(2)教員によるスタートカリキュラム開発
幼稚園・保育園生活と小学校生活のギャップを少なくし、スムーズに小学校生活に適応できるようにするためにスタートカリキュラム開発に取り組んだ。その背景として、本来、小学校入学までに身に付けるべき基本的生活習慣が定着していないまま学校に入って来る児童が目立ってきていた。着替えや給食に時間がかかる。午後の授業に寝てしまうなど、集団生活に適応できない児童がいる。また、幼稚園・保育園の保育方針も多様となり、園でのルールもいろいろである。そのため一斉指導が難しくなり、担任は生活指導に多くの時間を費やすことになり、学習指導にも影響が出ている。出来るだけ早く学校生活に溶け込めるよう、また、学ぶことへの興味を高めようとするのがタートカリキュラムである。その計画づくりを1年担任・養護教諭・スクールカウンセラーに担わせた。
1. 新1年生保護者会

資料1 新1年保護者会パワーポイント
基本的生活習慣の定着は家庭の力に負うところが大きい。基本的生活習慣定着のために、まず保護への啓発が重要だと考えた。そこで2月の新1年生保護者会は、たんに入学説明会とするのではなく、保護者の意識を啓発するためのパワーポイントを作成した。家庭で取り組んで欲しいことを養護教諭・栄養士・クールカウンセラーが芝居仕立で演じながら伝えた。パワーポイントでは、教室での1年生の現状をイラストで見せ、家庭で取り組んで欲しい項目を示した。多くの保護者は興味深げにスクリーンに視線を向けていた。
2. スタートカリキュラムによる授業展開
25年度入学直後の1年生の1週間分の授業計画を下記の表のように作成した。スタートカリキュラムには、時間の設定と指導者の2つの工夫がある。
入学当初の1年生にとって45分間の授業時間は集中力がもたない。そこで、1時間の45分を20分と25分に分け、2コマを設定し、学校生活の基礎を身に付けさせるようにした。また、教室には、学級担任の他に音楽専科、養護教諭、栄養士などの教職員にそれぞれの専門性を生かして指導に当たらせた。「安全な登下校」の指導については、警察のスクールサポーターに依頼するなど学校外の人材も招いた。
| 1日目 | 入学式 | |
|---|---|---|
| 2日目 | 1校時 |
学習の準備(1)(ランドセルのしまい方等) あいさつ・歌 |
| 2校時 |
靴箱・水道・トイレの使い方 下校の仕方 |
|
| 3日目 | 1校時 |
学習の準備(2)(お道具箱整理等) 返事・歌 |
| 2校時 |
整列の仕方 学校めぐり(整列歩行の練習) |
|
| 3校時 |
帰りの準備の仕方 絵本の読み聞かせ(1) |
|
| 4日目 | 1校時 |
学習の準備(3)(朝のしたく) 1年生を迎える会の練習 |
| 2校時 | 安全な登下校 | |
| 3校時 |
体操服の着替え 絵本の読み聞かせ(2) |
|
| 5日目 | 1校時 |
算数 しまたんけん 1年生を迎える会の練習 |
| 2校時 |
発育測定(体育着に着替えます) 給食(1)おいしい給食 |
|
| 3校時 |
1年生を迎える会の練習 学年遊び |
|
| 4校時 |
週末の帰りの支度(体育着・上履き) 絵本の読み聞かせ(3) |
|
【3】成果と課題
(1)成果
今回の最大の成果は就学児童の増加である。平成24年度は31名の新1年生を迎えたが、平成25年度は41名を得ることができ、実に12年ぶりに1年生が2学級編制となった。そのため、20名・21名の少人数の学級で、落ち着いた学級経営が可能となった。
また、1年生の指導にさまざまな教職員がかかわることで、よりきめ細かな指導ができるようになった。学級担任には精神的なゆとりができ、児童と豊かにかかわりができる。
このことは、児童の姿としても表れており、きまりが守れる学級の雰囲気であるため授業中の私語や立ち歩きがほとんど見られない。
(2)課題
就学児童の増加は平成25年度だけの一過性のものかどうかは、次年度を待ってみないと分からない。継続性が見られないと課題が解決されたとは言いがたい。
スタートカリキュラムは、1週間分のみ作成だったが、次年度は2週目の作成を今年度の反省を踏まえ作成したい。