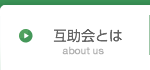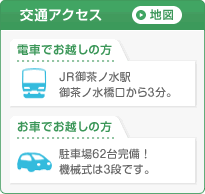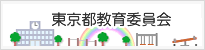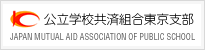職場の心理的安全性を高めて、いきいき働ける環境を
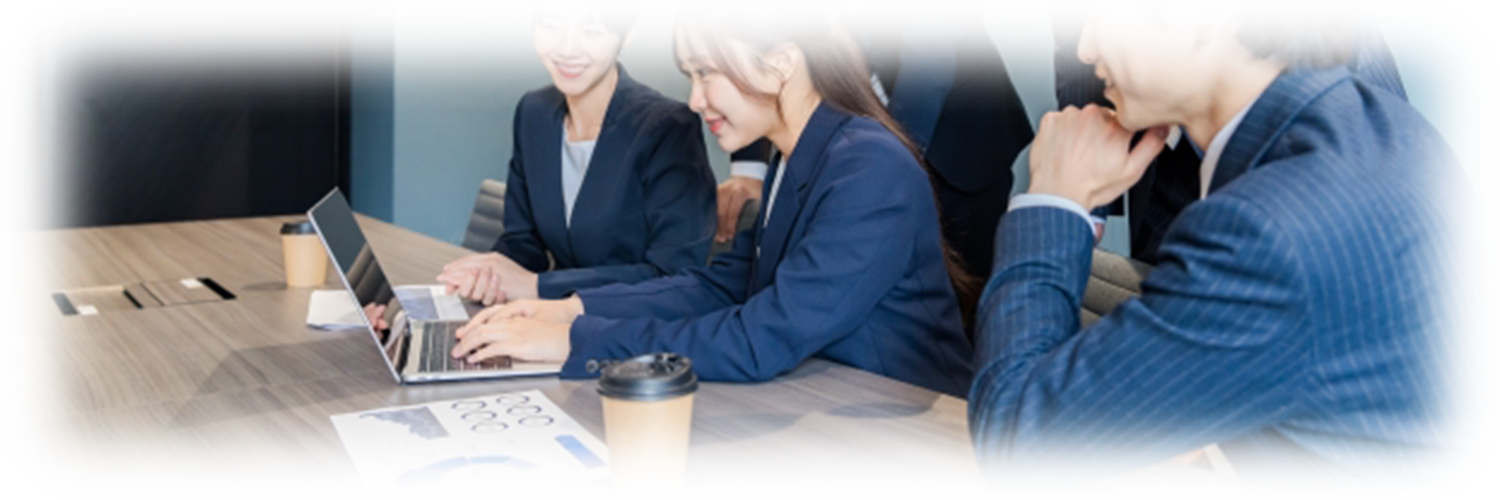
職場における心理的安全性を高めることが求められる時代となりました。心理的安全性とは、「スタッフが、そのチーム(部署、所属)で、気兼ねなく自由に発言したり行動したりできるかどうか」を示す概念、あり方、とされています。心理的安全性の高い職場、チームでは、組織の生産性向上に繋がる、職場環境を改善する、安心して職務が遂行できる、という効果やメリットが得られます。ストレスチェックの結果や集団分析に基づく職場環境改善と合わせて、職場のコミュニケーション、活性化につながる環境づくりのキーワードといえましょう。
ここで、心理的安全性の問題を、事例を通じて確認してみましょう。
(架空事例:Dさん 50代 女性 教員)
Dさんは、採用後30年程度勤続しているベテランです。
4月に異動しましたが、異動先の在籍年数の長い女性同僚数名からの支援が少なく、不慣れな業務でミスが発生しました。また、ミスや抜けが発生すると、嫌味を言われる、書類を無言で受け取られる、近くを通ると避けられるなど無視、嫌がらせと感じる状況が続きました。身体不調や不安、気分の落ち込みが続くため、こころの相談に来談しました。
(こころの相談にて)Dさんの状況や状態を把握し、職場不適応の可能性を伝え、精神科受診を勧めました。管理職に状況を話し、今後の対応を相談するよう助言して、相談を継続した。
相談では、同僚の言動態度への心理的な構えや割り切り方、切り替え方を助言しています。服薬はなく、主治医から職場環境の調整が必要との意見が出て、休業して職場を離れたことで一定程度体調が改善しました。上司にも職場環境の問題を伝え、理解を得ました。出勤訓練をしながら、学年や学部など所属するチームを調整された上で職場復帰をしました。新しい職場では未経験の業務や業務習得のために、積極的にコミュニケーションを取るように努め、徐々に職場に慣れ、所属チームへの安心感を感じ始めています。
このような職場環境や同僚の言動はハラスメントや嫌がらせにも該当するかもしれません。合わせて、ご本人は同僚の言動に委縮してしまい、人間関係作りや業務を円滑にするコミュニケーションが難しい状態、すなわち心理的安全性の乏しい環境であったと思われます。
職場のリーダーやチームを率いる役割を持つ主任や管理職などは、心理的安全性を意識してコミュニケーションや気軽に提案や意見を言える環境づくりに努めることが期待されます。
メンタル面や心身の不調、話しづらい内容などは、職場外に設置された、心理職による「こころの相談」を上手に活用いただければと思います。