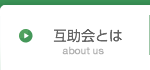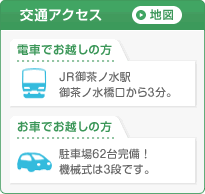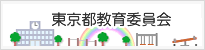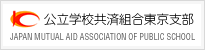外部人材活用事例の紹介
ボランティアの支援を受けて
日本語適応教室での指導
目黒区立東山小学校
校長 久保 栄
日本語適応教室担当主幹教諭 齋藤 寛治
1.学校紹介
本校は、目黒区の北部に位置し、公務員住宅に囲まれた学校で、開校53周年になる。
児童数968人で、その約2割(200人)が帰国・外国人児童である。開校当時から、帰国児童が多く、昭和44年に文化庁から帰国子女教育研究協力校に指定された。昭和58年には、目黒区が文部省の帰国子女教育受入推進地域に指定されたのに伴い、本校はそのセンターとして、帰国子女教育にますますカを入れ、その結果、第2回馬場賞(国際理解教育・帰国子女教育)を受賞するなど本校の教育活動は高く評価されている。また、過去にさかのぼれば、英語雑誌「TIME」が主催する英作文コンクールにも日本でただ一人入選を果たすなど、帰国児童の英語力は、全国的に見ても抜きん出ている。
帰国児童は、このような教育環境の中で、楽しくたくましく生活している。帰国児童が英語なまりで、校内放送をしてもその子を優しく見守っている校風があり、みんなが違っていて、一人一人が輝いている学校なのである。また、学校のホームページも開かれ、海外との海外からのアクセスも多い。さらには、毎年のように、海外からの大規模な訪問団を受け入れている「世界が身近に感じられる学校」である。
2.帰国児童の現状
近年の帰国児童の日本語力を見てみると、帰国児童の多くは、滞在国の現地校のみに通い、補習校に通ったり、通信教育を受けたりする児童はほとんどいなくなった。そのため、在留年数が少ないにもかかわらず、日本語力・国語力の低下が著しい児童が増加した。
従って、日本にもどっても、日本語力が編入学年からかけ離れるため、日本語を学ぼうとする学習意欲の低下が顕著な児童が多くなった。そのため、本人はもとより、保護者のメンタルケアが重要な課題となっている。帰国時における面談は、校長、副校長、担当が当たり、学習状況について詳しく聞くようにしてきた。
また、学佼週5日制の完全実施に伴い、土曜目の午後に行ってきた帰国児童のための日本語補習の日本適応教室と英語保持教室(現英語交流教室)を土曜目の午前中に実施するようになった。そのため、土曜日の午後に行ってきた時期は、帰国専任(現日本語加配教員)が、計画運営し、指導は、本校の教員が分担し、毎週行っていた。しかし、土曜日の午前に移ったため、日本語加配教員が一人で担当し指導を行うことになった。
そのため、児童6人程度をグループ学習させた時もあった。そのような状況でも充実した指導を行ってきた。やはり、年によっては、帰国児童の日本語能力の差が大きく、個に対応した指導ができにくい状況の時期もあった。そのため、このような状況をどのように改善させていくかが本校の課題であった。
そこで、平成20年1月から東京都教職互助会互助事業課によるボランティア事業の募集があったので、本校は試行的にその募集に参加し、その後、本格的にボランティア事業を活用し、帰国児童の日本語力向上を図っている。
また、帰国児童の日本語環境でのストレス緩和を目的にした英語交流教室とは、帰国児童の保護者の熱意に動かされて開設した一面があり、講師の人選等、その運営は、大変難しい教室である。しかし、円滑に運営するように保護者の協力も得ながら、平成19年度からは、講師謝礼を区の予算から充当して頂き、現在も継続的に行なっている。帰国児童にとっては、「心のよりどころ」になって、日本語力の向上にも役立っている。
3.本校の国際理解教育での日本語適応教室の位置づけ
永年、本校で取り組んできた国際理解教育は、数年に1回程度、研究発表を行っている。その際には、必ず、全体計画と年間計画を見直してきた。
平成22年度に研究発表した際、見直した全体計画にも、日本語適応教室が位置づけられている。<平成22年度 研究集録より>
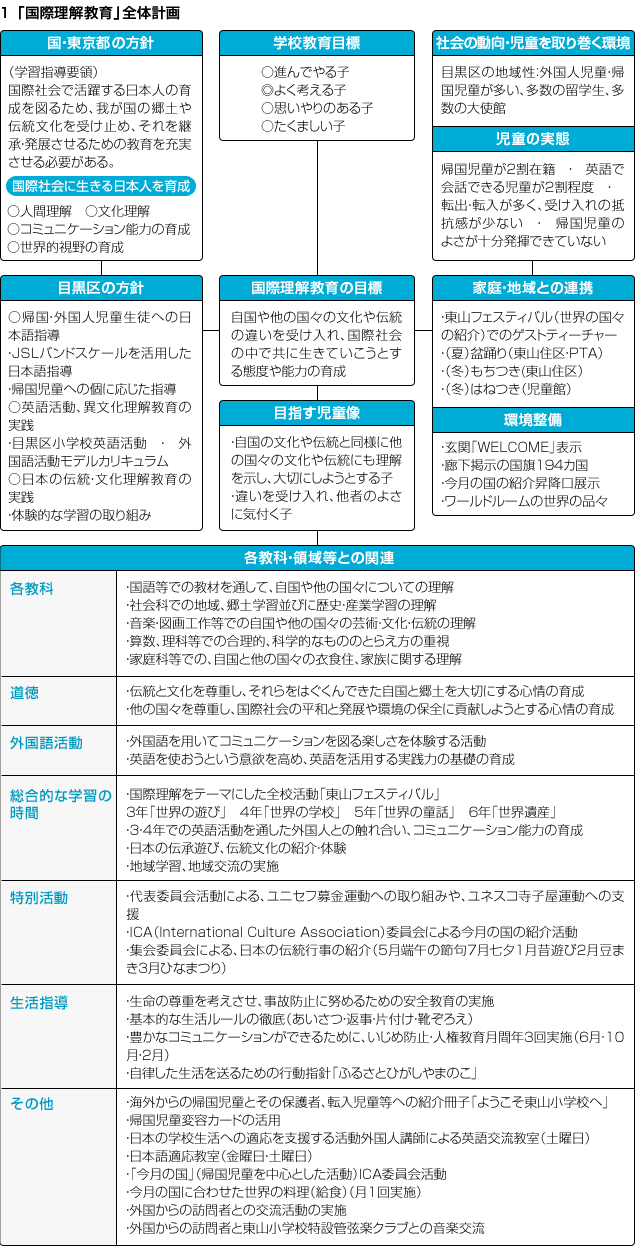
ボランティア活動の取り組みの状況
期間
5月から3月まで
※ 4月に保護者向けの説明会を実施する。
回数
年間26回 1回3時間(9時~12時 1回3時間)
※ 3連休や学校行事(運動会・全校授業参観・学芸会・もちつき大会)は閉室
内容
日本語の個別指導
- 伝統的な言語文化と国語の特質に関する指導
- 言語の特徴やきまりに関する事項
- 文字に関する事項 ※ 学習習慣に関する指導を含む
使用教材
国語の基本(光文書院)言語の学習(目黒区教育委員会)
対象児童
6人(3年1人 4年2人 5年3人)
※ 日本語加配担当4人は除く
対象児童の在留期間と在留国と日本語状況
 <3年A児 在留期間H17.9~H18.4 H20.9~H22.6 在留国 米国>
<3年A児 在留期間H17.9~H18.4 H20.9~H22.6 在留国 米国>
- 日常会話はできる。話好きではあるが文字が雑である。
- 日本語学習に対する学習意欲が低い。
- 英語力についての関心は高い。
<4年B児 在留期間H16.5~H18.4 H20.9~H22.6 在留国 米国>
- 日常会話はできる。自分から話したがらない。
- 日本語学習に対する意欲は高い。
- 英語力については関心が高い。
<4年C児 在留期間H13.5~H22.6 在留国 米国>
- 父親はオーストラリア人であり、家庭での会話は英語である。
- 日本語学習に対する学習意欲は高い。
- 英語は父親が教えている。
<5年D児 在留期間H19.6~H21.7 在留国 オーストリア>
- 日常会話はできるが、話の筋が通らないことがある。
- 目黒区学力調査の結果は、4年の学習内容が身についていない。
- 英語はほとんど話せないが、課外活動(特設管弦楽クラブには)参加。
 <5年E児 在留期間H20.8~H23.4 在留国 米国>
<5年E児 在留期間H20.8~H23.4 在留国 米国>
- 日常会話はできるが、自分の気持ちを言葉で表現するのが苦手。
- 語彙力も不足している。
- 英語力はある。
<5年F児 在留期間H17.12~H20.6 H20.8~H23.2 在留国 タイ>
- 日常会話はでき、受け答えもしっかりできる。
- 語彙力が不足している。
- 英語力もあり、英語に関心もある。
指導の流れ(1時間)
| 1.はじめ |
|
|---|---|
|
2.学習(1) 国語の基礎 ことばのきまり |
|
|
3.学習(2) 漢字の学習 |
|
| 4.まとめ |
|
指導の効果
1.学習意欲の向上
教職一筋で退職された講師であり、教職経験はとても豊かである。指導している児童に対する慈しみに富んだ言葉掛けは永年の指導に裏付けられたもので、得難い指導を帰国児童は受けている。講師と児童との人間的なふれあいと児童の潜在的な能力をも引き出すことができる指導力は、4年の学習内容から始まった児童が、編入学年である5年を終了し、6年の学習まで学習した児童がいたほどである。
2.正しい学習習慣を身に付ける
日本に帰ってきたばかりの帰国児童は、鉛筆の持ち方や椅子の座り方など、基本的な学習習慣が身についていないばかりか、在留国の学習習慣に影響されている場合も少なくない。そのため、椅子の座り方や鉛筆の持ち方も、在籍学級でも指導をするが、講師からも指導されて始めて身についた場合もある。むろん挨拶の習慣も身に付けさせるようにしている。
その他
来年度からは、区教育委員会から英語交流教室の水曜日開室が要望されており、日本語適応教室も水曜日開室を計画している。日本語加配教員が、平日に指導することは校務があり(職員会議等があるため)困難である。是非、講師の増員を希望し、1回の4人を指導できる体制を作りあげたい。