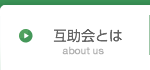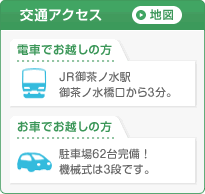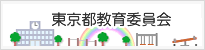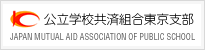教育研究グループ支援(研究成果報告)
研究の概要
特設「日本語」の指導
ねらい
- 豊かな人間性や社会性、国際社会に生きる日本人としての自覚を育成する。
- 日本人の母語である日本語を学ぶことにより、「知的生活の基盤」「コミュニケーション能力の基盤」「感性・情緒等の基盤」をつくる。
- 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を育てる。
- 古語や漢語を含む日本語を理解するとともに、自国の文化や伝統に触れ、自国の良さを体感し、継承しようとする資質や態度を育てる。
- 日本語を学ぶことにより、日本人としての豊かな教養の素地を培う。
主な内容
- 美しい日本語の語彙の習得につながるもの。
- 日本の古典や現代文学の名文・詩・俳句・和歌等の朗読・暗誦を重視する。
- 伝統的な遊びや歌(唱歌・わらべ唄など)などの体験・身体活動も含めた内容とする。
- 文化や年中行事・祝日などの理解・調べ学習等多様な活動を取り入れる。
- )自然や季節・風土などへの豊かな感性の基礎を磨くことができる教材を工夫する。
教育課程上の取り扱いについて
ア 低学年は年間10~11時間(余剰時間;学級活動)
イ 中学年は総合的な学習の時間の年間35時間活用。
ウ 高学年は総合的な学習の時間の年間35時間活用。
学習の基本パターンについて
【1】古文・漢詩・論語・短歌・俳句など
指導上の留意点
- 大きな声で、朗々と、調子よく・リズムを踏まえて音読・朗読する。
- 意味のだいたいを理解する。
- 暗誦する
- 情景を想像する。イメージする。
- 日本の自然、四季の変化などへの関心を持たせ、愛着を感じさせる。
主な学習活動例
- 範読を聞き、模倣する。
- 様々な形態で音読する。(斉読、グループ、個人、群読)
- 個々に音読・暗誦練習、発表する。
- 文章や語句の意味を話し合ったり、解説を聞いたりしながら、理解する。
- 想像したことやイメージなどを言葉で表現したり、簡単な絵などに描く。
- 文章を視写する。
- 歌曲の詩は、合唱を鑑賞したり、歌ったりする。
※各学年の実態に合わせて工夫する。
【2】年中行事・ことわざ・四文字熟語
指導上の留意点
- 調べる活動が中心になるが、難解なものは教えるという原則でよい。
- 四文字熟語で穴埋め式のゲーム化を図ったり、行事などでは絵を補足させたり、思い出日記にしたり、活動が単調にならないようにしたい。
主な学習活動例
- 読める・意味をだいたい理解するを中心にする。
- 格言や四文字熟語で使えるようにする。
【3】年中行事・ことわざ・四文字熟語
主な学習例
- 資料は白文、書き下し文、大意、教訓の順に並べてある。提示の仕方は、書き下し文、範読、素読をやり、白文の文字をバラバラに出し、並べてみたりしてもよい。また、白文を出し、読み方を予想させてから書き下し文を提示し、素読に入ってもよい。
- 素読(音読)を十分にやらせたい。また、暗誦にも取り組ませたい。
- 白文や書き下し文を視写する活動も大切である。
- 文の意味は、「大意」の部分を活用して解説する。
- 「教訓」の部分は、発達段階に応じて、かみくだいて説明するときに活用するとよい。
年間指導計画
平成22年度総合日本語 年間計画はこちらのPDFをご確認下さい。
主な実践例
(実践事例1) 第3学年 総合日本語指導案
(1)題材名 年中行事① 祝日① 百人一首 (複数題材)
(2)ねらい
- 代表的な年中行事を取り上げ、行事に込められた人々の願いを知る。
- 祝日について、その意義や背景を知るとともに、祝日をどのように迎えるかについて考える機会とする。
- 百人一首に慣れ親しむ。
| 主な学習活動 | ☆留意点 ●準備する物 |
|---|---|
1.学習のねらいや予定を知る。 2.4・5月の代表的な年中行事の意味を調べ、発表し合う。 3.4~8月で知っている祝日を発表する。 ○取り上げられた百人一首の意味を知り、情景・心情などを想像しながら暗誦する。 |
☆「年中行事」とは、1年の間に、何らかの目的や意味をもって、慣例として行われる行事であることを知る。 |
(3)授業後の反省
- 学習内容が盛りだくさんで、児童が十分に考える時間を確保できなかった。
- 行事や祝日で、何をどう取り上げるかを教師の側で精選しておくことが必要であった。
- どの子にも楽しく学習できるように、ワークシートを工夫したことが良かった。
- 「調べ学習」と「知識・理解」の学習を明確にした方が、児童の意欲を高める上で良いのではないか。
- 複数題材と、単題材を扱う時間を、教材内容を基に考慮することが大切である。
(実践事例2)第6学年 総合日本語指導案
(1)題材名 平家物語 (1題材を45分で扱う)
(2)ねらい
- 平家物語の一節を読み、大意をつかむとともに、そこに盛られた思想を考える。
- 暗誦を通して、音韻を楽しむ。
(3)主な学習活動
学習活動 |
☆留意点 ●準備する物 |
|---|---|
1.本時の学習のめあてを知る。 4.朗読練習、暗誦練習をする。 |
●平家物語の一節のプリント ☆教師の後を追って読ませる。 |
(4)授業を振り返って
- 一語一語の言葉の意味にとらわれて、文脈を想像して読むことが少しおろそかになった。
- それぞれの文章を基に、全体の大意を考えさせることがやや難しかった。
- 「無常観」を考えさせることで、当時の人々の思いを想像させることができたが、自分に振り返って考えさせるためには、時代背景をしっかりつかませる必要がある。
- 歴史学習との関連では、進度が合わず、社会科との関連として扱うには難しかった。
- 実際に琵琶法師による「弾き語り」のようなものを導入すると、より臨場感のある学習になったのではないか。
- どの月に扱うのかは、他教科との関連も明確にしながら考えていくとよい。
- 「調べ学習」として扱っても、題材そのものが難しいので、ある程度教師による補足で良いのではないか。
(実践事例3) 第6学年日本語授業記録
(1)題材名 古文「枕草子」
日本語の響きやリズムの美しさを味わおう
(2)目標
- 古文の表現に親しんだり、古文に描かれた情景を想像したりすることを通して、作品が書かれた時代のものの考え方や感じ方にふれる。
- 「枕草子」の学習を通して、古典に対して興味・関心を抱く。
(3)学習の展開
主な学習活動・発問 |
児童の反応 |
|---|---|
1.学習する古文を知り、見通しをもつ。 |
 ・徒然 草 ・女の人、平安時代の人、紫式部のライバル ・「やうやう」「だちたる」「たなびきたる」「あかりて」「やまぎは」 ・明け方 ・明るくなって ・春は明け方が美しい瞬間  |
(4)授業を振り返って
- 全文を読んで、季節ごとの比較をすると、「春はあけぼの 夏は夜 秋は夕暮れ 冬はつとめて」となり、季 節ごとの「一日の中での美しい時間・瞬間」に子供たちも着目しやすい。また、当時の平安貴族たちの「自然に対する感性」にふれやすいのではないか。
- 春はあけぼの 夏は○○
秋は夕暮れ 冬は○○
というように、季節毎の違いを明確にすると、「あけぼの」がよりはっきりと焦点化でき、考えやすかったのではないか。 - 最後の「自分だったらーー」という学習で、清少納言との「春」のイメージとの違いを際だたせることができた。
実践を振り替えって
主な成果
- 当初のねらいである「国際社会に生きる日本人としての自覚を育成する」ために、自国の伝統や文化を理解させるという点では効果的な指導であったといえる。児童に意図的・系統的に「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を育てる」ためには、さらに指導法の改善に努め、児童が意欲的に学習できるようにしていきたい。
- 「古語や漢語を含む日本語を理解するとともに、自国の文化や伝統に触れ、自国のよさを体感し、継承しようとする資質や態度を育てる」ためには、「日本語」指導とともに、体験的な学習も取り入れ、そのよさを体験的に理解することが必要である。また、実際に文化や伝統を継承し、発展させようとしている多くの人とのふれ合いの中から、思いや考えに触れさせることも大切である。
- 暗誦や朗読などを通して、日本語の美しさにふれる機会を日常的に設けるとともに、「百人一首大会」や「朗読大会」を取り入れることで、児童の意欲を育てることができた。
課題
- 低学年は、余剰時間を設けて「日本語」指導を行うことができたが、3年生以上で「総合的な学習の時間」で指導していくには、より「横断的・総合的」な学習として組み立てていくことが求められる。「自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育成する」ために、小単元での学習計画をしっかりと立て、「探求的学習」へと改善していくことが必要である。
- 学級指導の中に、「日本語」を取り扱う場を設け、年中行事や祝日に対する指導を行っていくことが必要である。
- 総合的な学習の時間における「国際理解教育」の活動として、「自国理解」「伝統文化」の学習に位置付け、指導していくことが必要である。
- こうした位置づけの基に、従前行ってきた「日本語」指導の改善・充実を図っていく。