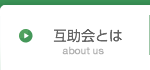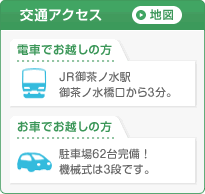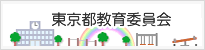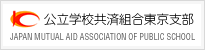受診やカウンセリングのタイミングについて

年々、メンタルヘルスに対する理解が進んでおり、ストレスやうつ病といったこころの問題も、からだの健康問題と同じように治療やケアする必要がある、という認識が広まりつつあります。精神科や心療内科などに受診したり、カウンセリングを利用したりすることも、社会的に受け入れられやすくなってきました。
からだの不調は痛みなど明確な症状が自覚できますが、こころの不調はからだの症状よりも自覚しにくく、認識することが難しい場合があります。ご相談に来られる方からも、「どういうタイミングで受診すればいいのか分からない」「受診すると、どうなるの」といった受診に関する質問や、「どういう時にカウンセリングに行けばいいの」「カウンセリングでは何ができるのでしょう」などのカウンセリングに関するご質問をいただくことが、しばしばあります。
そこで、A先生の架空事例を取り上げながら、受診やカウンセリングについてご紹介したいと思います。
【架空事例:同僚との関係が上手くいかない30代女性】
A先生は、とても活発で意欲の高い方ですが、不注意なところや、優先順位を立てることが苦手な傾向にあり、以前から、与えられた仕事が期限内にできないことが多く、ご自身も困っていました。4月に異動し、新しい学校で頑張っていこうと思っていましたが、行事の準備や校務分掌など、与えられた役割が遂行できず、多くの教員とトラブルが起きるようになりました。A先生は、学校内でイライラとして不機嫌な様子を見せる一方で、トイレや更衣室などでよく泣いている姿が見られ、遅刻や突発休が増えてきました。そうした様子を心配した同僚のB先生が、A先生に声をかけると、A先生は「周りの先生から注意を受けることがつらい。自分が責められているようで苦しい」と話しました。同僚のB先生は、A先生に医療機関への受診を勧め、その後A先生は自宅近くのメンタルクリニックを受診し、治療とカウンセリングを始めることになりました。
医療機関でできる支援
A先生が同僚に「辛い」、「苦しい」と伝えているように、A先生ご自身が感じている苦しい状態と、同僚B先生からみても心配になるようなA先生の様子について、そうした様子が症状や医学的に支援すべきかどうかを医師の診察によって検討することができます。医師の判断によって、今の症状に合わせてどのような治療を進めていくのか、病気や症状に関すること、今後の仕事や私生活など日常生活のことなどについて、説明を受けることなどができます。
カウンセリングでできる支援
カウンセリングでは、A先生がどのようなことに困っていて、どのようなことを辛く感じているのかなどをカウンセラーと一緒に整理していくことができます。自分がストレスになりやすいポイントについて、一緒に考えて対策を立てたり、コミュニケーションの方法について練習することができます。
精神的な不安や問題を感じる場合は、できるだけ早めに医療機関を受診されることをお勧めしますが、カウンセリングについては、明らかな症状や困り感がない場合でもカウンセラーに相談することができます。自分について向き合いたい、自己理解を深めたい、誰に相談したら良いかわからない、これからどうしていけば良いのかなどを、カウンセラーと一緒に考えていくことで、自分に合った対処法などを見つけやすくなります。カウンセリングは、こころの健康を維持するためのメンテナンスやセルフケアのお手伝いもできますので、ご興味のある方は是非こころの相談をご利用ください。